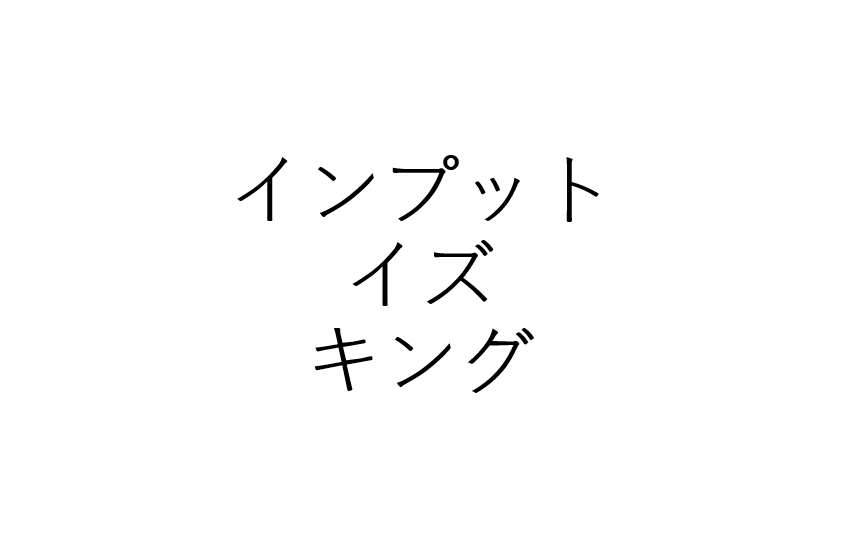 さて前回まではイケてる事業の見分け方を解説してきました。
さて前回まではイケてる事業の見分け方を解説してきました。
見分けるポイントやコツをお伝えしてきましたが、考え方があるとはいえ、判断するためには自分の「定規」をたくさん持たないとダメでしたね。
定規は圧倒的な情報のインプットから作られます。
ということで、今回はそのインプットの手段【初級編】についてご紹介します。
インプットが圧倒的に足りていない人の特徴
突然ですが、以下に心当たりはありませんか?
- インプットが足りてるかどうかよくわからない
- 何をインプットしないといけないかわからない
当てはまる方は圧倒的にインプットが足りていない状態です。
「何が分からないかが分からない」という状態です。
誰しも最初はそうなので気にする必要は無いのですが、即効性のある解決法なんてないということは重要なポイントです。
これさえ読んどけば良いとか、この人のツイートをウォッチしておけば良いとか、そんな都合の良い話はありません。
キャズムを超えるまでは我慢してインプットあるのみです。
その1:書籍からインプット
体系的に学びたいときや深く知りたいときには書籍が圧倒的に良いです。
繰り返しになりますが「何を読んだら良いかわからない」という方は圧倒的に読書量が足りていません。
「何を読んだら良いかはわかる」まではジャンル絞らず手当たり次第に読みましょう。
本をたくさん読みたくなる本
余談ですが、私は学生時代に成毛さんのこの本を読んで多読になりました。
10冊同時は極端ですが、1冊読んだら次の本へというスタイルを捨て、5冊くらいを常に並行して読むスタイルになりました。
当時の私にとっては衝撃的な、圧倒的納得感を得た本です。
詳しくは本書に譲りますが簡単にまとめると、
- 電車、授業の待ち時間、リビング、自宅トイレ、ベッドなど、シーンごとに読む本を固定する
→システマチックに多読する - 精読よりも多読
→多読すると、ある本の説明が分かりにくかったとしても別の本でしっくりくるとかある - 最後まで読む必要はない
→読むのは大事なとこだけで良い。もったいないからと全部読むのは時間コストを考えていない - 同時に読むと混同しないの?
→ありえない。人間は頭が良い。また、同時に読むことで点と点が有機的につながる
という内容です。
その2:Webメディア
Webの記事は、紙と比べて速報性や多様性が強みです。
ブログや記事なら手軽に執筆できるということもあってか、短いのに書籍よりも価値ある記事はたくさんあります。
古典的ですが、私はfeedlyに集約して読んでいます。
キュレーションでは読みたい記事があまり出てこないのです。
一部ですが、
- 決算が読めるようになるマガジン(https://irnote.com/)
- Stockclip(https://www.stockclip.net/)
- TechCrunch(https://jp.techcrunch.com/)
- THE BRIDGE(http://thebridge.jp/)
- The Startup(http://thestartup.jp/)
- 戯言学園(http://www.zaregoto-gakuen.com/)
その3:Twitter
情報感度が高く、自らの経験や考えを(=1次情報)を発信する人をフォローします。
スタートアップ経営者やVC、エンジェル投資家などは感度の高いツイートを積極的に発信されています。
また、「サブスクリプション」とか「Saas」みたいな界隈の人しか使わないような単語で検索する手もあります。
こちらもごく一部ですがご紹介すると、
渡邉 宏明(Hiroaki Watanabe) (@hiroaki_naberun) | Twitter
Ken Nishimura / 西村賢 (@knsmr) | Twitter
Hiro Maeda (前田ヒロ)@ BEENEXT (@djtokyo) | Twitter
Yusuke Nozoe (@yusuke_nozoe) | Twitter
sho/AnyMind@バンコク (@Shoooooou_sc_7) | Twitter
廣川航(`・ω・´) (@tosyokainoouzi) | Twitter
たなかたかゆき(パピコ) (@papico_chupa) | Twitter
茶色いネコ (@chairoineko8) | Twitter
大手町のランダムウォーカー (@OTE_WALK) | Twitter
その4:キュレーションメディア
Googleアラート
なにが知りたいか見えてきた人向け。
キーワードを登録しておくと、その単語に関連する記事を毎日通知してくれます。
NewsPicks
NewsPicks(https://newspicks.com/)
最近はオジサマのメディアとなりつつあるNPですが、自称識者のコメントが勉強になることも。
最後に
以上、情報収集のためのソースについてご紹介してきました。
大事なことなので3回目でも言います(笑)が、「なにが足りないか分からない」状態のときは、食わず嫌いや偏読はやめて、片っ端から読むようにすると良いと思います。
歴史、芸術、エッセイ、小説なども読んでいるうちにだんだん掴めてきますよ。
なお私は最初経済学と並行してアガサクリスティにはまりました笑
みなさんも多読を極めて情報をシャワーのようにたくさん浴びることを習慣化されてはいかがでしょうか。